●「つかみ」を一番大切にする開発スタイル
―――もう少し詳しく、作り方について伺っていきます。一般的にゲーム制作では、3つのプロセスがありますよね。ゲームの方向性や世界観などを決定し、技術検証なども行う準備段階。全体の見本となるようなパートを作って、仕様を固める段階。最後に決まった仕様に基づいて、データを量産する段階です。御社においても、こうした基本的なプロセスは同じと考えて良いでしょうか?
山本:大まかな流れはその通りですが、その中でも自分たちは、ゲームの核となる部分を、最初に徹底的に固めます。ディレクターが一番こだわっているポイントで、そのゲームのウリになる部分ですね。自分たちは「つかみ」と呼んでいますが、そこをまず明確にしないと、面白いゲームにはならないんで。それが確立するまでは、量産体制に入らないのがポリシーです。
―――どういった部分が「つかみ」になるのですか?
山本:たとえば戦闘のおもしろさがウリであれば、主人公と敵キャラクターとの攻防に特化して作り込みます。この段階でさっきも言ったように、ちょっと動くモノができたら、みんなで寄ってたかって、ああでもない、こうでもないと言い合いながら、作っては壊しを繰り返します。
―――なるほど。
山本:そこがしっかり固まった上で量産体制を敷くんですが、そこでもまた、ああでもない、こうでもないを繰り返していきます。その結果、どんどんステージやキャラクターが増えていって、結果的に世界観も広がっていきます。『BAYONETTA』などは、まさにそんな感じで進んでいって、当初予定していた内容とは、大きくかけ離れていきました。
―――初期に予定していた世界観やストーリーなどと、すりあわせは行いますか?
山本:それは作っていきながら、ディレクターや、みんなで考えていきます。一番大事なのはゲームとしての面白さなので、辻褄をあわせることではないですから。必ずしも最初に決めたものに、こだわることはないんです。
―――ちなみに『VANQUISH』では、何が「つかみ」だったんでしょうか?
大谷:プレイヤーが超高速で移動する「ブースト」ですね。
山口:シューターでは、遮蔽物に隠れながら、敵をちょっとずつ倒していくプレイスタイルが多いんです。ところがディレクターの三上真司は、それは嫌だと。もっとアクティブで、スピーディで、どんどん前に突っ込める「ハイスピード&ハイテンション」なシューターにしたいというのが、コンセプトでした。そこから、いろんなネタ出しをして、面白さを検証していったんです。その結果として、本作で特徴的な「ブースト」というアクションが生まれたり、「ARモード」という一定時間だけ周りの動きを遅くさせる機能が加わりました。
 |
| 前へ、前へ、のアクションが魅力的な『VANQUISH』 |
―――では、最初にテストケースとして、このステージを作って仕様を固めましょう、といった感じではないんですね。
山口:はい、全然違います。敵のデザインも最初はもっとメカ風だったんですよ。それが検証の結果、撃って倒した爽快感は、やっぱり人型の方が高いということになって、人型ロボットになりました。そんな風に検証を繰り返しながら、わかったことがたくさんあって、最終的に今の形に落ち着いた、という感じです。
―――では『MAX ANARCHY』の「つかみ」というのも・・・。
村中:「オンラインで多人数の乱戦格闘アクション」ですね。ここを徹底的に検証して、作り込みました。その根底部分はぶらさずに、今は付随している要素について、さまざまな検証を重ねながら、どんどん広げています。
―――コンセプトが、バシッと一言で説明できる点が、すごいですね。「ハイスピード&ハイテンション」とか、「オンラインで多人数の乱戦格闘アクション」とか。
村中:改めて言われると、そうかもしれませんね。
●格好いいだけじゃなく、いかにゲームに組み込めるか
―――もう一つ、御社のアクションゲームは「ベヨ様」を筆頭に、キャラクターがユニークですね。しかもキャラクターデザインやイメージイラストを、外部に発注するといった行為が、少ないように思います。
西村:そうしたスタイルをとることもありますし、全然否定しているわけではありません。ただ、何かキャラ絵を一枚描いてもらって、それで終わりというようなことは、弊社では考えにくいですね。最低でも週に何度か来てもらって、デザインをチームのスタッフと一緒にこねくりまわさないと、アクションゲームとして良いモノにならないんで。だったら最初から、がっつり中で作りましょう、ということになりがちなんです。
小手川:ベヨネッタも全身真っ黒の方が、イラストとしてはカッコ良いんですな。でも、彼女は両手に白い手袋をはめているんですよ。それから髪には赤くて長いリボンをしていて、両手・両足には大きくて真っ赤な銃がついています。背中も大きく空いていて、プレイヤーに対して肌が見えている。これはすべて、ゲームで遊びやすくするためです。そういうのが、ゲーム的に良いデザインなんです。
井上:あの形に落ち着くまでに、すごく時間がかかっているんですよ。
西村:僕らはゲームを作っているんで、モニターに映ったモノがすべてなんですよ。しかもゲーム画面って、状況に応じてフィルターやエフェクトがかかったりして、どんどん色味が変わっていきます。その時にユーザーにわかりにくかったら、いくら紙の上で良いデザインでも、あんまり意味がないんですよ。そのため開発をしながら、デザインをガンガン修正していくんです。
山口:主人公キャラクターの場合は特に、プレイヤーの操作でカメラの角度や距離などが変わるので、どんな状況でも視認性や遊びやすさが求められます。だから余計に変わっていきますね。
大谷:プログラマーの立場からすれば、敵キャラクターの絵を見ると「このデザインで、どんな攻撃ができるだろう」と、すぐに考えます。じゃあ、このデザインをベースに、こんな風にしたら、もっと良くなるんじゃないかとか。そうしたことの積み重ねで、ゲームのクオリティが格段に変わるんです。
小手川:逆にダメ出しを受けたときに「このデザインに、こだわりがありますから」なんて言われると、先に進まない。それは絵描きとしては良くても、ゲームになった時のことを、想像できていないということですね。
 |
| ベヨネッタもサムもゲームにすることで映えるキャラクター |
―――なるほど。そうやってどんどん、変わっていくわけですね。こうしたことがキャラクターデザインだけでなく、すべてのパートで存在する。
山口:そうですね。パッと見て良くても、ゲームに組み込んだときに、全然ダメだから・・・という理由でリテイクを出されることは、山のようにあります。特にキャラクターアニメーションでは多いですね。そんな時に「何を言っているんだ、おれは格好いい動きが付けられば良いんだ」という人だと、難しいでしょうね。
小手川:だから、柔軟性がある人だと良いですね。ダメ出しされて、意固地になっちゃう人じゃなくて、何がダメなのか理解して、それを自分の糧にできる人が理想です。
●現場スタッフそれぞれのアクションゲーム観
―――そうした現場主導の作り方というのが、アクションゲームに向くんでしょうか? テストプレイを繰り返しながら、作っている印象を受けました。
山本:ああ、そうでしょうね。そうした作り方は、ずっと大事にしています。やっぱりアクションゲームは、触ってナンボなので。みんなで開発途中のモノをみて、コントローラを触って、いろいろ意見を出し合うのが大事じゃないかな。誰か一人の意見に、右へならえで作っているわけじゃないから。
―――皆さんにとって、アクションゲームって何でしょう?
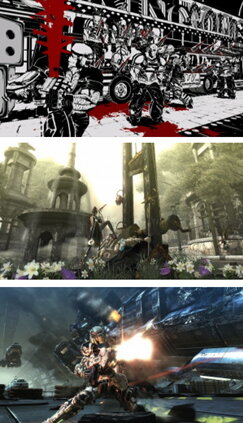 |
| 上から『MADWORLD』『BAYONETTA』『VANQUISH』アクションゲームを作り続けてきたプラチナゲームズ |
大谷:僕は単純に動かして楽しいモノがアクションゲームかなと。基本はそれだけです。その上で、遊び相手としての敵キャラクターがいる。その遊び相手がバラエティ豊かだと、さらに面白い。僕は主に敵キャラクターのプログラムを担当しているので、そこに思い入れがありますね。
小手川:僕も確かに、自分ではそんなにアクションゲームを遊ばない方なんです。何かハードルがあって、それを乗り越える楽しさでしょうか。あとは何か癖のあるモノが好きなんですよね。たとえば、すごく癖のある車を乗りこなす的な楽しさです。うまく乗りこなせない時と、乗りこなせた時の落差を楽しむようなモノかなと。
山口:僕はアクションゲームが一番好きですし、自分でも良くプレイします。アクションゲームって、一番コンピュータゲームらしいと思うんですよ。基本的にリニアに時間が流れる中で、反射神経を駆使して、直感的に操作をして楽しむ遊びで、コンピュータ以外だと実現できないですからね。それに遊んでいると、陶酔感や没頭感が生まれてきて、それがすごく気持ちが良かったりする。もっとも、レベルの低いアクションゲームだと、そうはならない。そうした快感をユーザーの皆さんに提供したいですね。
西村:僕は雑魚敵のアニメ−ションを作ることが多いんですが、僕の中では雑魚敵って、優秀なサンドバッグみたいな位置づけなんです。いかにプレイヤーに緊張感を持ってもらいつつ、気持ちよく殴ってもらえるか。そうしたリズム感をうまく提供できるように、注意して作っています。
村中:思わず没頭してしまって、ゲームの中に入り込めるようなアクションゲームが理想ですね。そのためには操作感やレスポンスが大事で、そうでないと触って気持ちいいゲームにならないんです。僕はずっと主人公のアニメーションを担当していますが、操作して格好いいアクションの設計とか、自分が係わったキャラクターをゲーム中で操作できる点が魅力だし、作っていて楽しいところです。
山本:アクションゲームは直感的に遊べて、プレイヤーにゲームの気持ちよさが一番ダイレクトに伝わるジャンルなので、作り手側のセンスがものすごく問われるんですよ。数フレーム単位での調整が入るか、入らないかで、手触りが全然違うんですね。それをどこまで突き詰められるかが、作っていて楽しいところです。実際、タイトルごとに新しい発見がありますし、常に勉強になりますよ。
●『MAX ANARCHY』での挑戦
―――そういえば皆さんは、アクションゲーム以外を作られたことはありますか?
井上:アクションばっかりやなあ。だって『バイオハザード』だって、アクションゲームだと思って作っていたし。
村中:僕は前の会社で、いろんなジャンルのゲームを作りました。釣りゲームとか、レースゲームとか。もちろんアクションゲームも作りましたが、この会社ほど密度の高いゲーム作りでは、なかったですね。
大谷:僕も他のジャンルのゲームを作ったことはありますが、基本的な作り方の部分は、同じだと思うんです。作っては壊して、の繰り返しという。
―――村中さん、小手川さん、大谷さんは最新作『MAX ANARCHY』の開発に参加されていらっしゃいますね。それぞれ、どういった点に挑戦されているか、教えてください。
村中:これまでのタイトルはみな、主人公が1人でしたが、本作ではマルチプレイヤーゲームということで、複数の主人公格のキャラクターが同じ画面内で、同時に登場します。そこで全体の意識として、各キャラクターの個性づけをしっかりしよう、と考えました。その中で自分としては、動きだけを見ても、どんなキャラクターかわかるように、個性的なアニメーションづけを心がけました。
小手川:キャラクターモデリングでも、普通は主人公キャラに一番力を割くんですが、今回はプレイヤーキャラが複数いるので、そういうわけにもいきません。一体あたりのポリゴン数なども減ってしまいます。それでも他のゲームに比べて見劣りしないように、どれだけ作り込めるか苦労しました。
大谷:プログラム的には、たくさんのプレイヤーキャラクターが同時に登場して、さまざまな状況が発生しても、処理落ちしないように気を遣いました。少しの処理落ちでも、ゲームの印象は大きく変わってくるので。ネットワーク部分についても、弊社では初となる試みで、さまざまな課題がありましたが、がんばってクリアしたいと思います。
 |
 |
| 多人数プレイが核となるという『MAX ANARCHY』 |
●「ゲームを作りたい人」に来て欲しい
―――本座談会はリクルート目的も兼ねているのですが、どんな人に来てもらいたいか、イメージを教えてください。
山本:ゲームを作りたい人に来て欲しいですね。ゲームを遊ぶのが大好きという人でなくてもいいので、ゲームを作りたい人。最近は新卒でも、ゲームを作りたくてゲーム会社に就職活動をする人が、減っているんですよ。それよりも就職活動の一環として、たとえば学校でCGを勉強したので、映像関係の1ジャンルとして、ゲーム会社を受けました、という人が多いんです。うちの場合はみんなでゲームを作っているので、どんな職種でも、ゲームを作りたい人に来て欲しいですね。
小手川:今の職場では、納得のいくゲームづくりが出来なくて不満がたまっている人。自分が本当に作りたいゲームを作りたい、という人もいいですね。何か作りたい欲求があって、そのためには何でもするという、熱意と、どん欲さを兼ね備えている人。
井上:やっぱり、ゲームが好きな人。そして根性がある人に来て欲しいですね。好きじゃないと根性も持てないし、嫌々やってると、だんだん根性がすり減っていくので、結局逃げ出しちゃうんです。好きという気持ちの中にこそ、根性が生まれてくるはずなので。今はゲーム側に軸足がなくても、入ってから「こっち側」に来てもらって、ガンガン頑張ったら、いいと思うんです。
山口:よその会社のことは、良くわからないですが、やっぱり作り方が大幅に違うところがあるようなので、そこは柔軟に考えて欲しいですね。他の会社さんでゲームデザイナーがやるようなことまで、グラフィックデザイナーやプログラマーがやることになるので、そういうのが嫌だという人は、向いてないかもしれません。一回頭を柔らかくして、同じゲームでも、いろんな作り方があるんですよって感じで、捉えてもらえれば。
井上:今までの仕事に飽き足りない、もっとガンガンとゲームを作りたい、という人は、ぜひ来てください。嫌でもやらされますんで。
大谷:これまでグラフィックデザイナーだったけど、弊社でディレクターになった人もいます。そういった転職でも、うちはアリです。
―――他に「ベヨネッタ」でSEを担当された方も、楽器メーカーの営業からの転職組だと、以前お聞きしました。ゲーム業界が細分化・専門化していく中で、そうした経歴の持ち主は、ずいぶん減りましたね。
小手川:わざわざ、そういった経歴の人間が集まってくるのが、ウチらしいんじゃないでしょうかね。
●大阪の会社、東京の会社
―――ちなみに、皆さん大阪の方なんですか?
小手川:出身はけっこうバラバラですね。生粋の大阪生まれは、ほとんどいないです。
井上:関西圏の人間は多いですね。
山口:会社全体で言えば、東京から中途入社で来たスタッフも、4割くらいいますよ。当たり前の話ですが、東京の方がゲーム会社が多いので。
―――大阪でゲームを作る良さはありますか?
山口:ゲーム会社が少ないので、良くも悪くもガラパゴス化していますよね。
山本:関西弁なんで、ダメ出しも言いやすいというか。
山口:いやいや、はじめて関西に来たときは、恐かったですよ。なんでこの人たちは、いつも怒っているんだろうって(笑)。
―――ゲーム会社が少ないから、集中して作れるという良さも、あるんでしょうか?
西村:どうでしょう。東京の会社で仕事をしたことがないので。ぼんやりとしたイメージしか浮かばないんですよ。ただ、最近はあんまり元気がなさそうに見えるので、その辺は、なんでかなあ。
―――東京のゲーム開発者には、どんな印象を持たれていますか?
大谷:どこか印象が薄いというか。おとなしい人が多いというか。イメージですが。
井上:うちらが逆に濃すぎて、なじみにくいのかなあ。
山口:東京からの転職となると、引っ越しして来られることになるので、そこで覚悟が必要だし、敷居も高くなりますよね。ただ、みんな恐い人じゃないんで。いったん中に入って、なじんでもらえれば、楽しくやれるんじゃないでしょうか。
―――プライベートでの交流はありますか?
井上:僕は会社を一歩出れば、完全シャットアウト型です(笑)。
西村:飲み会とかは結構ありますね。新しい人がきたら、とりあえず飲みに行こうか、みたいな。あとはプライベートで、バスケのチームを作って活動しているスタッフもいます。
村中:同じ趣味の者どうしで、釣りに行ったりとか。
山口:ただ、そういうのを強く押し出すような会社ではないですね。僕が知らないだけかもしれませんが。
山本:自由なんですよ。だから飲み会なども、会社主導でやるというよりは、みんな好き勝手に飲みに行く、みたいな感じです。
●「日本代表」としてゲームを作る意味
 |
| 「GO NEXT PLATINUM」を掲げ次のステージを目指す |
―――公式サイトで「日本代表として世界で闘う」というページも公開されています。
井上:ほかの会社さんのことは、よくわからないんですが。最近は日本中で元気がない会社さんが多いのかな、などと感じていまして・・・。うちは世界に向けて頑張っていくぞ、ということだと思っています。
山本:もともと、うちのメンバーは昔から世界で闘ってきたんですよ。それがプラチナゲームズとして再スタートしてから、5年が経過して、知名度もそれなりに高まってきた。そこで、改めて決意表明をしたという感じでしょうか。直球でゲームを作る。まがいものは作らない。ゲームの中身だけなら、世界のどこにも負けない。そんな宣言です。
―――なぜプラチナゲームズは、世界で闘えるのだと思いますか?
小手川:集まったメンバーが良かった、というのはあるんじゃないでしょうか。
井上:アクションゲームの根幹の、触って気持ちが良いという部分は、日本人も外国人も同じなんじゃないかなあ。そこが得意ジャンルだったのはラッキーでしたね。
山本:たぶん技術力云々じゃなくて、意識の問題だと思います。基本的に毎回やりきろうとしているよね。
山口:ゲームに対しての意識の高さは、たぶんどこにも負けないと思います。みんな妥協をしないから、自ずとそれなりのモノができているんじゃないかなあ。
小手川:売り上げにしろ、人気にしろ、国内と海外でどちらかに偏ることが、あまりないんですよ。昔から特に意識はしていないんですが。
山口:海外に受けるゲームって何だろうって、悩んだ時期もあったんですが、今はもう考えてないですね。自分たちが面白いとか、格好いいと思えるものを作れば、結果的に世界でも受け入れてもらえる、ということが見えてきたんです。逆に他社さんのタイトルで、海外受けを無理して狙って、失敗しているところも多いですよね。
井上:まず自分たちが楽しいゲームを作っているんですよ。お客様が遊んで楽しいゲームを作るというのは、実は建前であって。なんだかんだいって、自分たちが楽しいから作っていて、その延長線上にお客様がいる、というのが本音なんです。それで結果的に世界中の人たちが楽しんでくれればラッキー、みたいな。
小手川:自分たちが楽しくなければ、ユーザーだって楽しくないでしょう。
山本:逆に「アクションゲームを作れ」と上から言われて、現場が嫌々作ったゲームって、触ったらそれだけで、わかっちゃうんですよ。
山口:僕らは、そういうスタイルは絶対にとりたくないですね。実際、他社さんのゲームを触って、純粋にゲーム要素だけで悔しいなって感じることは、なかなかないんです。もっとこう変えたら、もっと気持ちよくなるのに、と思うことがほとんどなんです。
―――長時間にわたって、ありがとうございました。
 |
| 参加者のみなさん |
「自分たちはゲームを作っている」「ゲームを作りたい人に来て欲しい」・・・。座談会中に何度も、同じフレーズが繰り返されました。現場のスタッフがみな、同じ意識を共有して、同じ目線を向いている点が、同社の強さの秘密なのだと、改めて感じさせられました。
ゲーム業界に限らず、クリエイターはみな、エゴイストの集団です。自分が作ったモノが世界で一番優れていると、心の中では誰もが思っています。逆に、そうでなければクリエイターには、なれません。ゲーム開発でも、みな魂を削りながら、グラフィックデータやプログラムを作り続けています。
そうした成果物に対して、時に理不尽とも感じられるダメ出しや、自分の責任ではないところで、さまざまな手戻りが発生する・・・。通常なら、モチベーションが一気に下がる瞬間です。「そんなの、最初から言ってくれよ」と怒りをぶちまける人がいても、おかしくないでしょう。
その言葉を飲み込み、時には笑いに変えて、スクラップ&ビルドを続けられる。それを支えているのが「世界一のアクションゲームを作っている」というプライドであり、これまでの実績なのでしょう。そうした一段上のレイヤーの充実感や喜びを、自分たちと一緒に体験して欲しい。座談会を通して、そんなメッセージが感じられました。
みんなで、わーっと集まって、やいのやいの言いながら作っていく・・・。こうした「古き良き」開発スタイルは、さまざまな理由から、急速に失われつつあるのが実情です。大前提として、優秀なリーダーと熟練した現場、そして人材育成システムが必要です。しかし、そこにこそ日本のゲーム開発の未来があるのかもしれません。
BAYONETTA(ベヨネッタ) (C)SEGA
MAX ANARCHY(マックス アナーキー) (C)SEGA
VANQUISH(ヴァンキッシュ) (C)SEGA
MADWORLD(マッドワールド) (C)SEGA. SEGA, the SEGA logo and MADWORLD are registered trademarks or trademarks of SEGA Corporation.
特集:プラチナゲームズ
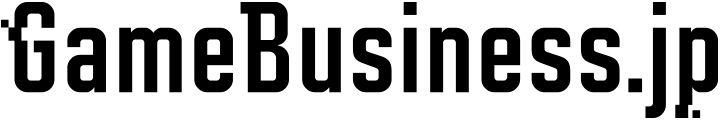












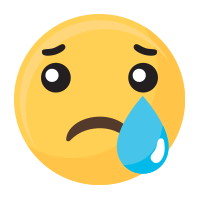













※コメントを投稿する際は「利用規約」を必ずご確認ください