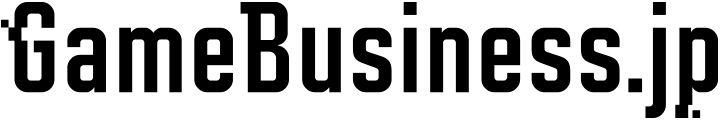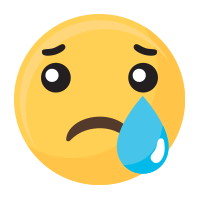2019年1月17日にコンソール版が発売された、バンダイナムコエンターテインメントのフライトシューティング『エースコンバット7 スカイズ・アンノウン(ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN)』。『エースコンバット』シリーズが、ナムコのアーケードゲーム『エアーコンバット』をベースに開発されていたことはよく知られていますが、実際にシリーズ始祖のコンセプトについて現在まで明らかになったことはありません。
今回のインタビューは、最新作を含めシリーズをより深く知るために、『エースコンバット』の始祖となるアーケードゲームの1つ1995年3月に稼働した『エアーコンバット22』(以下、『22』)の開発スタッフである、『22』ディレクターの大村純氏(『エースコンバット7』では開発プロデューサー)と、夛湖久治氏(『エースコンバット7』ではVRモードディレクター、現在は『7』DLCディレクター)のお2人に話を聞きました。
『エアーコンバット』と『エアーコンバット22』誕生の経緯だけでなく、開発者から見た90年代中盤当時のアーケードゲーム事情や、最新作『エースコンバット7』の関係性も語られた貴重なインタビューとなったので、内容的に数ページに渡る量となりましたが是非とも最後までご覧ください。

■『エアーコンバット22』の始まりと90年代当時の「バーチャルリアリティ」
――今回は貴重な機会を設けていただきありがとうございます。それではよろしくお願いします。始めにお二人の自己紹介をお願いします。
大村氏: 1993年に新卒としてナムコへ入社した大村純です。中・大型のアーケードゲームの開発部署に関わり、初めて担当させてもらった製品が『エアーコンバット22』でした。
元々飛行機が好きで、「飛行機もののゲームを作りたい!」とアピールしていたら、たまたま初代『エアーコンバット』(以下、初代『エアー』)の続編を作る話があったことから、『22』への開発に参加する形となりました。
その後も色々なゲームの開発に関わる事ができまして、ラインナップで言えば、池袋にあるテーマパーク「ナンジャタウン」にかつて設置されていたHMDアトラクション『ファイヤーブル』、レースゲーム「レースオン!」などを担当しました。
その後は家庭用の部署に移り、レースゲーム『MotoGP』や『デス バイ ディグリーズ』、『ソウルキャリバーIII』、『アイドルマスター』シリーズなどにも関わりました。

この後はプロジェクトのバックサポートが主な仕事になっていきますが、『エースコンバット』は『エースコンバット インフィニティ』と、最新作の『エースコンバット7』に関わりました。とくに後者では開発プロデューサーを担当させていただきました。
夛湖氏: 私は大村の入社翌年となる1994年に入社しました。大村と違って、「飛行機が好き」ということを言っていたわけではなく、上司に「ミリタリーファンです!」と言っていたら「丁度良いところがあるよ!」と言われて、連れられて来たのが大村のいた『22』……。当時は『エアーコンバットII(仮)』と呼んでいて、頼まれる形で開発に関わりました。ただ、当時はアーケードゲームの開発スピードが速く、1年もかからない内に完成までもってこられる事に加え、人数が少なくても進められる規模でした。

大村氏: チームも小さかったですし、内容も今のゲームタイトルと比べると(開発規模は)コンパクトでしたね
夛湖氏: (開発に参加した時は)基板の入れ替えで大騒ぎしている感じで、当時はSYSTEM 22から最新のSYSTEM SUPER 22へアップグレードしていた時でした。(アセットを)作るものとしては、たくさんあったわけではなかったので、テキストエディタのEmacsを使って内部データを見たり、ゲームで遊んで調整したり、仕様書の内容を学んでいました。
当時いくつかのプロダクトライン(開発段階)があったのですけれど、この(『22』の)仕様書に書かれている「P2」という文字は、量産一歩手前の最後の作り込みの段階です。
その時点で分厚い仕様書が出てくるのが珍しかったのですよね。大抵皆「最終仕様書」という会社の書庫に入れる前の最後の資料として一生懸命書くというのが定番でした。
※SYSTEM 22: テクスチャマップングが可能となったナムコのアーケード基板。『リッジレーサー』や『サイバーコマンド』などが採用。
※SYSTEM SUPER 22: SYSTEM 22に2Dの拡縮機能を追加したアーケード基板。『エアーコンバット22』や『タイムクライシス』などが採用。
大村氏: 『22』の開発チーム内に僕の先輩社員でプログラマーの人がいたのですが、その人から「『開発は仕様書ありき』が基本なんだよ」とのお話があって、「だったら、できるだけしっかり書こう!」ということで色々勉強させてもらいながら書いていましたね。
夛湖氏: (その先輩は)志の高い人で色々なものを作っていただいて、遊びの部分でも隠し機能的な「ミサイル連射モード」を作っていただいたほど心優しい方でもありました(笑)。
また『22』には、サウンドスタッフとして川田宏行氏がいたりしましたね。有名なところでは、過去にはスペースシューティングゲーム『スターラスター』の曲を書いていた人物だったりします。
大村氏: 当時はプロジェクトと言っても、今と比べると本当に小さい開発規模でしたね。
夛湖氏: ナムコのアーケード開発では、まず当時横浜市港北区にあった「開発設計部」と呼ばれている部署で、ハードウェアのデザインやメカ部分を開発し、当時横浜市神奈川区にあったYCC(横浜クリエイティブセンター)でソフトウェア開発を行っていました。
ソフトウェアに関しては1部屋に9人集まって開発していました。ビジュアルアセットは外部に委託していましたが、それも3名ほどでしたね。最新作の『エースコンバット7』の開発とかと比べるとアリみたいな少ない人数ですね。いま考れば凄いことですね。
――当初は『エアーコンバットII(仮)』と呼ばれていたのですね。ところで『エアーコンバットII(仮)』の企画書表紙にある「VR本部長」という欄があるのですが、これにはどんな意味があるのでしょうか?
夛湖氏: 中・大型機って体験・体感ベースのゲームじゃないですか、それがバーチャルリアリティに繋がるため当時ナムコが「VR開発本部」という志の高い名前を付けたと上司からは聞いています(笑)。本当かどうかはわかりませんが(笑)。(ナムコの「体験ベース」に関する意気込みは『エースコンバット7』VRモードTXMセッションで詳しく説明)。
大村氏: 当時は「バーチャルリアリティ」という名前がもてはやされた時代でしたので、積極的にVRゲームを開発していく部署ということで付けられたものですね
夛湖氏: その当時は他のゲームメーカーでも「バーチャル」を頭文字に持ってきたタイトルが幾つかありましたしね。 我々が入社する3~4年前の1990年には『ギャラクシアン3』が出ていたじゃないですか。
当時のパンフレットの表紙には「VRの序章」とありました。体験・体感型ゲームは総じてVRと記載され、会社として事業意識があったようです。しかしながら、我々としてはそこまで追いつかず「意識高い名前だな」と。どちらかと言えば、その下部組織であり所属組織でもある「開発企画部」の名称を我々は使っていました。
大村氏: 当時は企画書を出しても「この企画はバーチャルリアリティじゃないからだめ!」と言われたこともありましたね
夛湖氏: 今のHMDゴーグルを装着するスタイルの「バーチャルリアリティ」は、プレイヤー自身の特に視覚に頼った体験・体感がメインですが、それを別の形で表現していた時代でしたね
大村氏: (90年代中盤のゲームでは)3DCGがポリゴンだけの存在からテクスチャを貼れるようになり、一段と本物らしさが増して、ゲームへの没入感が増した時代なんですよ。本当に「バーチャルリアリティ」が世間的にも興味津々だった時代ですね。
夛湖氏: 加えて『22』では、基板がSYSTEM 22からSYSTEM SUPER 22へとアップグレードされたことで、特にポリゴンの量は変わりないですが、表現出来る幅が広がったのです。
具体的には、SYSTEM 22がSUPERになる時に2D面が強化されました。計器類をポリゴンで作らなくてもスプライトを貼ればOKとなったため、それまでポリゴンで描いていたものをゲームに割り振る事が出来るようになりました。
――実は2019年2月に、初代『エアーコンバット』が関東で唯一商業施設にて稼働が確認されている埼玉東部のラウンドワン栗橋店に向かい、同作を実際にプレイしてきました。そこで現在の『エースコンバット7』へと続く流れの源流をプレイ出来たのですが、『22』のSD筐体版は開発されなかったのでしょうか?
夛湖氏: SD筐体にSYSTEM SUPER 22が入れられなかったのですよね。そのためDX筐体オンリーだったんですよ。
大村氏: 法律(電取法)上の観点から、試験にクリアしないと入れられなかったんです。
夛湖氏: SYSTEM SUPER 22は基板が4枚になったのですが、基板間を繋ぐフラットケーブルからのノイズがきつくて…。そのため、SD筐体には『22』が入らなかったんですよ。あとDX筐体はとてもコストがかかるんで、結局『22』はそんなに数が出せなかったんですよね…。
――DX筐体はどれぐらいコストが掛かったんですか?
大村氏: このDX筐体は初代『エアー』からの物だったので、自分は筐体のデザインに触れていないのですが、凝ったデザインで本物感があって最高でしたね
夛湖氏: デバッグを何度しても飽きませんでしたね。「何故ここ(装飾パネル)のボタンが押せないんですか!?」と言った覚えがあります(笑)
ハード設計の方から聞いた話では、初代『エアー』のDX筐体には、コストの高い成形品をフロントパネルを筆頭にいたるところで使っているため、かなりの高額だったとのことです。この筐体の高価格化が問題だったため、『22』は既存DX筐体をステッカー等で改造する方向となっていました。
※筆者補足: 当時としては筐体にかなり予算が掛かったタイトルがスキー体感ゲーム『アルペンレーサー』で、『エアーコンバット』DX筐体はそれに迫る価格だったとのこと
大村氏: このDX筐体の大型ディスプレイにはステッカーが貼ってあって『22』用に化粧してありますけれど、ディスプレイとして使っていた三管式リヤプロジェクションモニターは汎用品なので、基本的には量産効果が高いものなのです。
夛湖氏: 大体高い順に、本体→本体化粧類(外装成形品)→照光看板→ディスプレイですね。また可動筐体の場合は、本体下にあるベースの強度がないといけないために、その部分がさらにお高くなります。懐かしい話ですね。
――ディスプレイの方がお安いとは驚きでした!ちなみに『エースコンバット』シリーズの始祖となる『エアーコンバット』が誕生した経緯について何か聞かれた事がありますか?
大村氏: 普通の中学生や高校生の男の子だったら「戦闘機のパイロット」というのは普通に憧れますし、常日頃から思っていなくても映画「トップガン」などを見たら心が熱くなったりするじゃないですか。
そういう形で「戦闘機題材のゲームを出したら、きっと喜んで遊んでもらえるに違いない!」ということを当時の『エアー』の企画担当者は考えていたようです。
夛湖氏: この初代『エアー』企画書概案を読んでいただくとわかるのですが、現在の『エースコンバット』のコンセプトそのままで「ゲームはプレイヤーがヒーローの気分を味わえるような演出を行います」と書かれています。

大村氏: また当初の筐体案も「本当に戦闘機に乗り込んでいる感覚」を大事にしていたため、戦闘機の外観を含めたコックピットの形を模していましたが、それが洗練された結果、このDX筐体の形に収まったようです。
夛湖氏: 当時の先輩が言っていたことですが、その戦闘機の機首を模した初期案は外側の成形品や化粧を導入すると高すぎるため、最終的に取り外したと聞いています。私としては、初期案よりコックピットだけになったDX筐体の方がカッコイイと思いますね。
他にも筐体の可動も狙っていたとも聞いていました。しかしこれもより高価になるため色々な部分を削り落とした結果がDX筐体になったとも聞いています。また『エアーコンバット』の通信対戦のチェックもしていましたね。
大村氏:『22』ではなく初代『エアー』を2台使って通信対戦のテストはしましたが、諸事情ありまして商品化を目指しての開発にまでは至りませんでした。
夛湖氏: 当時大村から聞いていて覚えているのですけれど、結局その通信対戦は1対1だったので「ドッグファイトで互いに相手の後ろを追いかけ続けることになり、ゲームではなく作業になってしまう」というのを聞いて、入社したての私の心が崩れそうになりました(笑)「対戦したら面白そうと思っていたんですけれど!『ファイナルラップ』とかあるじゃないですか!」みたいな(笑)
大村氏: ただ現実的なところでは、「もっと多数対多数にすればゲームになる可能性はありそうだけど、そうすると基板能力的にとか、販売価格的に…」という事情もありましたね。
夛湖氏: これも聞いた話なのですが、初代『エアー』には当初ラダーペダルを入れる案もあったようです。しかしながら、導入すると余りにも難しくなるから外したとも言っていましたね。
大村氏: それは正解だと思いますね。フライトシミュレーターとして作っているつもりではなく、あくまでシューティングゲームとして開発していましたから。それによほど飛行機が好きなと言うか詳しい人じゃないと、ラダーペダルなんて知らないと思いますし。
――今シリーズの「歴史の始まり」を目撃しました…とても感動しています!確かに『エアー』のゲームシステムでラダーが加わると更に複雑で難しくなりすぎるかなと思いました。
夛湖氏: 初代に比べて『22』のほうが確かにエンタメ度は高いですね。自分たちが遊んでいるときも、エンタメ的な面白さは突き詰めて追っていた記憶があります。
狙いとしては、遊んでいて楽しいSTGであって、シミュレーターを作っているわけではなかったです。「演出はリアルでもいいけれど、ゲームは楽しくないと駄目」と言われた覚えがあります。
大村氏: 続編の『22』はSYSTEM SUPER 22となり、1フレームあたり4000枚と性能が上がったので敵が複数出せるようになりました。
初代『エアー』のSYSTEM 21は1フレームあたり1000枚しかポリゴンが描画できなくて(いずれも60fpsで動作)、自機と敵1機を描画するのが精一杯なんですよ。途中で2機僚機が付くシーンはありますが、限定的な場面でしか描写できなくて、どうしても1 vs 1のゲームになってしまいました。
『22』は敵機を複数登場させられるため、どの敵から落とすべきかという攻略法も生まれてくるので、それを素直に作りましたね。
夛湖氏: ミサイル発射制限はありましたけどね!(笑)
大村氏: 初代もそうだと思いますが、『22』は基本的に「機銃で撃ち落とす」ゲームにしたつもりです。敵機がチャフを放出してミサイルを妨害しますけど、ミサイルはロックオンして撃った後は自動的に追尾して敵を撃ち落とし、ゲーム性も低くなってしまうので、テクニックを活かした空中戦が楽しめるように機銃だけでもクリアできるように調整しました。
次ページ: 『エアーコンバット』と『エースコンバット』はどこで繋がったのか?