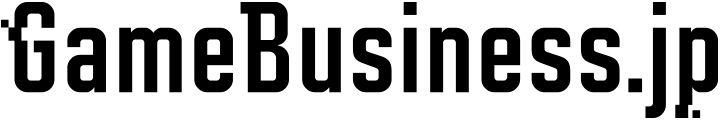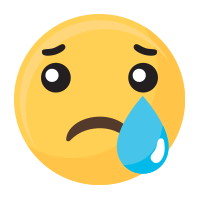ゲームに「メッセージ性」は必要か

宴も進み、話は『仁王2』だけにとどまらず、クリエイターとしてのゲーム観へと推移していく。私は取材を進めるにあたって、終始”どこまで聞いてよいのか”がわからなかった。しかしながら、制作者としてのルーツを覗こうとするのならば、当然様々な作品に触れなければならない。
安田「私自身は、メッセージ性の強いゲームは好きですしよく遊びますが、それでもゲームはゲームだと考えてます。線引きはとても難しいけど、”映画的な面白さを体験するゲーム”を遊んだときに、それを”映画ではなくゲームで作った理由”は見出せないんですよね。遠回りに感じてしまって。
Team NINJAとしても、私はまず”触って楽しい”というものを作りたいと考えてます。ゲームを通して重大な何かを受け取る……そういったものを作ろうとまでは思わないですね。でも、そうしたものを求める人は多いのかな?
批判という訳ではなくて、そうしたメッセージ性の強いものを作ろうと突き進める人というのは、とても純粋なディレクター・プロデューサーなんだと思いますね。それでも私自身は、あまりメッセージ性の強いものを狙おうとすると、作ったゲーム性から離れていってしまうような気がしています。それはアドベンチャーのような映像なのか、それとも、映像のようなアドベンチャーなのか」

総じて「裏を読み取る」雰囲気をまといがちなソウルライクジャンルの中にあっては、『仁王』シリーズは活劇という言葉が似合う作風である。もちろん哲学的な要素を忌避するほどのものではないが、『仁王2』で妖怪らしさというケレン味がより色濃くなったのも、ゲーム性から離れすぎてプレイヤーが遊びを見失わないようにするためだ。
もちろんこうした設計は制作者の思想が反映されやすいところだろう。哲学的なものを練り込もうと思えば当然、形は変わってくるに違いない。「触って楽しい」を目指して集中したスタンスは、初対面の私でも親しみやすさを感じた安田の人柄と無関係ではないに違いない。
批判を恐れずに言えば、メッセージ性の強さを目指したクリエイターは、そのアーティスティックな強さを壁のように感じてしまうことがある(もちろん、それは美点でもある)。当然ながら私にはその実態を知る由もないが、安田はコーエーテクモゲームス・Team NINJAの中で、カリスマ的な先導をするタイプではないはずだ。
2019年9月の東京ゲームショウや、今回の取材、また2020年2月に行われたプレミアム体験会の席上にあっても、安田はどんな相手であれ常に変わらない柔らかさを見せていた。決して強烈な印象ではないにも関わらず、すぐに”話しやすく・頼りがいのある人物”だと感じられる雰囲気を持っている。
制作現場の中では、全体に対して細かい目標を明確に設定しながら、それぞれの現場を下支えするような形で奔走しているのが、安田という人物なのだろう。

安田「元々は映画の道に入りたかったですね。技術を持っている訳ではないので、色んな人にお願いをしたり、調整をしたり……そうして段々と進んでいき、形になった時に楽しいと感じます」
どんな相手でも変わらない態度で接する安田は、また同時に「視点を合わせる」のも巧みだった。時にわざとらしく砕けてみたり、自分の弱さを認めてみたり、客観的に自身を見つめているのがわかる。現に、ライターとしての私が短い時間の中でさえ、現実離れした超人のような印象を受けることはなく、人間同士の関係を大事にする、地に足をつけた人物に思えた。
安田「ゲームの制作は当然苦しいこともあるし、納得いかないこともたくさんありますよね。ムカつくことだってありますよ。でも、楽しいなって思います」
ひとりの意見は大きい

様々なゲームの取材をしていると、どうしても「会社的」な仕事の中に身を置くこととなる。組織である以上、そうした渉外は大切な事であるし、もちろん全てを見せる訳にはいかない。体験版を繰り返して意見を集めていった彼らに、私はひとりのプレイヤー、またはゲームメディアのひとりの読者として質問を投げかけてみた。
安田「ユーザーレビューはかなり読みますよ。読みすぎてるかも。何なら、色んな掲示板まで読みに行くこともありますね。厳しい意見だなと思うこともあります。でも、大事な情報ですよね。全てには答えられないんですけど、最後まで高めていきたいなって思います」
金子「プレイヤーが意見を送ろうとするとき、果たして開発側へ届くのだろうかという思いは分かるような気がしますね。かつて自分にも、”客”の視点として似たようなことがありました。意見の全ては当然反映できない、という意味では伝わっていないように思われてしまうのかもしれませんけど、プレイヤーの皆さんが感じられているよりも、ずっと開発者との距離は近いんじゃないかと思います。それほど、ひとつひとつの意見を見ていますし、日々悩んでますね」
吉松「サウンドって、敢えて言葉にして意見を貰えることって実は少ないんです。それだけに、意見を頂けたときには大きな影響力があると感じてます。たとえそれがひとりからだけの意見で、ほぼ全てのプレイヤーがわざわざ送らないようなものだったとしても、そのひとりの意見はやっぱり大きく見えますね。ですから、レビューや意見というのは、思ったよりも開発者へ伝わっているはずです」

取材人として彼らと接するべきなのか、ひとりのゲーム好きとして臨むべきなのか……。私に与えられた一瞬のチャンスは、読者と開発者の橋渡しのためのものだと感じられた。
ゲームを制作する会社は、同じような場所がひとつとして存在していない。泥臭いやり方のところもあれば、システマティックなところもある。ちょっとした取材の猶予も得られないこともある中で、『仁王2』の彼らは等身大の姿で私達を受け入れてくれた。
この記事を書き上げることで、ゲームを愛する多くのプレイヤーが、能動的に様々な意見を制作者達へ伝えようとする発露のひとつとなれるのならば、ライターとしてこれほど幸せなことはない。