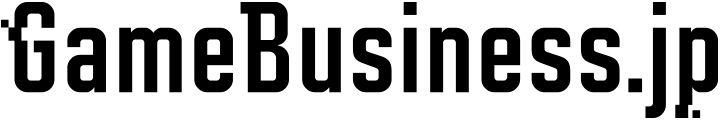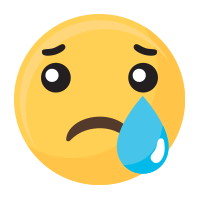『Bloodborne』プロデューサー山際氏との対談が実現

2020年2月14日……品川のソニー・インタラクティブエンタテインメントへと向かったのは、『Bloodborne』山際眞晃プロデューサーとの対談を収録する為であった。この対談を実現できるかどうかは、続く取材の中でも山場と言えるものだった。
『仁王2』を山際にプレイしてもらいながらの対談という、挑戦的なスタイル。取材を続けていく中で私は、失礼ながらArchipelのメンバーが「日本人ではない」ことの強さを感じざるを得なかった(決してズルいとは書くまい)。しかし、それらはArchipelのメンバーが秘める日本のゲーム業界に対する情熱の表出でもある。
いったい、私達を含めた日本のどのゲームメディアが、ここまで情熱的な活動を実際に行ってしまえるだろうか。それでも、彼らだからこそできること、そして私達だからこそできることは、それぞれ異なるはずだ。日本のゲーム業界の強さとも弱さとも言える「体制的」な部分を彼らがこじ開けようとするならば、それは彼らの明確な実力であることに違いはない。

安田「自分がディレクターやプロデューサーとして働く時に、信頼されるようになってきたなって思う瞬間ってありましたか。いきなりってことはないじゃないですか」
山際「要求に応えられたときですかね。しかもちょっと無理めな要求(笑)。当たり前ですけど、ひとつずつ信頼を勝ち取っていくしかないですよね」
安田「開発チームが同じ会社の人達ではない場合もあるじゃないですか」
山際「何者?っていうところから始まりますよね(笑)。品定めじゃないですけど。僕の場合は、外部のディレクターと話すことが多いのですが、ディレクターって面白い人が多いじゃないですか。なので、その人に興味を持つ内に、段々とプライベートでも接するようになっていきますね。そういう所でも関係性は深まっていくんじゃないですかね」
安田「何かを発表するようなタイミングとかで、チームの結束が高まったなと感じたような瞬間ってありましたか」
山際「『Bloodborne』に関して言えば、gamescomで実機のプレイ映像を出したときですかね。それに対するユーザーさんの反応がとても良くて、盛り上がってくれて……。チームや社内でも手応えがあって、これはいけるんじゃないかとなりましたね。そこからユーザーさんに応援してもらいつつ、進めてこれたって感じだったと思います」

山際「取材といえばなんですけど、『仁王2』を作るにあたって、日本全国津々浦々、見て回ったんですか?それとももうコエテクさんには知見があるからそうでもないんですかね?」
安田「いや、見て回りましたね。それこそ『仁王』の時はロンドンにも行きました。背景チームが行くことが多かったですかね。京都などの建物を撮影しに行って来るよって、撮った写真を渡したんですけど、全然使えないって言われて(笑)」
山際「分かります。背景を担当する人達って見るポイントが違いますよね。『Bloodborne』でも取材を行ったのですが、僕も色々撮ってみるんですけど、何にも役に立たなくて……そんなGoogleですぐ調べられるようなのいらないって(笑)。細かい部分、例えば、階段の手すりとかにみんな興奮してましたよ」
安田「ゲームのレベルデザインの参考としてもそうした現地の視察は役に立ちましたね。確かにこの構造ならつい行きたくなるな、といったような。お城は元々攻め込まれることを想定して作られてますけど、細かい所は実際に見て初めて”だからこうなってるのか”が理解できたり」
会話をしながら何度もやられてしまう山際氏に、安田が時折アドバイスを与えつつ対談が進んでいく。言わばライバル関係とも呼べるはずの相手に直接ゲームプレイをさせているというのはどういった感情なのだろうか。少なくとも、両者の間には見定めるような空気は感じられない。同じような立場の仕事に携わるものとして、似た苦労を共有するかのような質問が続いていた。

山際「『仁王2』で一番変わったのってやっぱり妖怪ですか?」
安田「そうですね。前作は史実の要素が強めだったんですけど、プレイヤーさんの反応は妖怪に対してのものの方が良かったと思います。海外のプレイヤーさんも、やはり妖怪の方が反応としては良くて、もちろん歴史にハマって調べたことで”このキャラクター本当にいたんだ”と興味を持って頂いたってパターンもありましたが」
山際「『仁王』で妖怪を出すのは、はじめから狙っていたんですかね」
安田「いえ、最初は実は妖怪の要素がなく、人間の敵だけだったんです。でも、アクションゲームとして厳しすぎるなと判断しまして。ストイックすぎるよなと。武器の種類でなんとかしてみようとは、当初から考えてたんですけどね
それに、妖怪であれば色んなことができますよね。何でもありというか。でも、日本人であれば何となくイメージできるものもあったりして、見ればわかるというのも強みだと思います」

山際「すいません、ちょっとコイツだけ倒してください」
安田「いいですよ。 ……これはこれで緊張しますね(笑)」
山際「あーほら、いきなりヤバいですよ!! 前のイベントでも同じようなことがありましたね。安田さんにイイところ与えようとして交代したらすぐ死んじゃって」
強敵に詰まっていたところでプレイヤーを交代し、ゲームに興じる二人。同じゲームを通じて仲を深めるというのは、どうやら年齢も立場も関係ないようだ。
山際「あっ、今のはなんですか?」
安田「大型の妖怪でも、この紫色のゲージを削ると、人間の敵と同じように強力な攻撃を当てられるんですよ。大技を返して倒してやろうと欲を出すと死んじゃうってパターンですけどね」
山際「そんなのあったのかあ……ちゃんと最初にプレゼンしてくださいよ(笑)」

取材はステージボスを撃破するまで続けられた。ボスとの戦闘に集中する山際氏のプレイを「フレーム回避型のスタイルですね」などと評する安田。「『Bloodborne』のクセが出ましたかね……」と返す山際氏。
両作をプレイされた方ならお分かりだろう。似ているジャンルとはいえ、そのエッセンスは明確に異なるものを柱としている。一瞬の操作のひとつひとつが、それぞれの作品の味として確立しているのだ。一緒にゲームを遊ぶ時の、ああでもないこうでもないと語り合うあの楽しさが、両者の間には流れていた。
山際「──今回は”どっち”に寄せようと思ったんですか?」
安田「決めてはいなかったんです。はじめのうちは前作『仁王』の全てを扱えてはじめて攻略できる……といったような、厳しい方向に行こうとしていたのは事実です。それでも見極めるのは難しかったので、体験版で反応を見ていきました」
山際「前作もそうでしたけど、かなり打ち出してましたよね。いや、本当にその方針はスゴイし、大変そうだなと思っていましたよ。確かに、難しいかどうかというより、理不尽になっていないかとか、そちらの方が見極めなきゃいけない所ですよね」
安田「まさにそうですね。難しいと思う人も、簡単だったと思う人もどちらもいる中で、大切なのは”続けてきちんと遊べるか”だと思っていて。それでも開発をしていると感覚がマヒしていってしまいますから、体験版を繰り返していく感じでしたね」
山際「前作も遊んだんですけど、『仁王2』は前作の感覚を少なくともそのまま味わえる感触はありましたね。そこは安心できるなと思いました。追加された要素については、今日試した時間でしか判断はできませんけど、やろうと思えば色んな遊び方ができそうだな、と楽しみになりました」