【CEDEC 2010】バーチャルペットと画像認識 ― 「画像認識技術とゲーム・インターフェイス」
画像認識は実際のゲームにどのように活かされているのでしょうか。
その他
その他
画像認識は実際のゲームにどのように活かされているのでしょうか。
この記事の感想は?




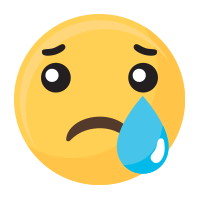
 『Ghost of Tsushima』の舞台、対馬にある和多都美神社が観光目的での参入禁止に―オーバーツーリズム訴え「崇敬者」のみ受け入れる姿勢
『Ghost of Tsushima』の舞台、対馬にある和多都美神社が観光目的での参入禁止に―オーバーツーリズム訴え「崇敬者」のみ受け入れる姿勢
神様に対する尊崇、崇敬の念をもってきちんとお参りする「氏子…
 リマスター版『The Last of Us』シリーズなどに携わったVisual Artsでレイオフ実施―PlayStation Studios Malaysiaのチームも対象とスタッフ報告も
リマスター版『The Last of Us』シリーズなどに携わったVisual Artsでレイオフ実施―PlayStation Studios Malaysiaのチームも対象とスタッフ報告も
 「高くても売れる」PS5 Pro効果でハード販売23%増―新CEOが描くソニーの"脱コングロマリット"戦略【ゲーム企業の決算を読む】
「高くても売れる」PS5 Pro効果でハード販売23%増―新CEOが描くソニーの"脱コングロマリット"戦略【ゲーム企業の決算を読む】
 2026年よりPS Plusフリープレイ&ゲームカタログはPS5向けゲームが中心に。PS4向けは減少へ
2026年よりPS Plusフリープレイ&ゲームカタログはPS5向けゲームが中心に。PS4向けは減少へ

人気ニュースランキングや特集をお届け…メルマガ会員はこちら