【GTMF2013】ゲストセッション 『箱 ! -OPEN ME-』が活用したミドルウェアとAR技術
見るべきところがあるのは大きなタイトルばかりではありません。PlayStation Vita『箱 ! -OPEN ME-』の有限会社 JetRayLogicがGTMFのゲストセッションに登場しました。
その他
その他
見るべきところがあるのは大きなタイトルばかりではありません。PlayStation Vita『箱 ! -OPEN ME-』の有限会社 JetRayLogicがGTMFのゲストセッションに登場しました。
この記事の感想は?




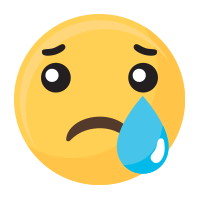

人気ニュースランキングや特集をお届け…メルマガ会員はこちら