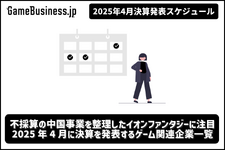今回インタビューしたブロックチェーン資産発行プラットフォームのEnjinでは、大人気ゲーム『マインクラフト』で利用可能なNFTを発行できる取り組みもスタートしています。
ゲーム内にブロックチェーン技術を取り入れることで、具体的にはどのようなメリットがあるのでしょうか。前述したEnjinの平手宏志朗氏(事業開発担当)に改めてブロックチェーン技術の解説から、現在の市場状況についてなど、様々なお話を伺いました。
●インタビュイー
平手宏志朗氏

2020年4月から、Enjinの日本市場を中心に事業開発を担当。ブロックチェーン技術に未来と可能性を感じこの業界に飛び込む。金融とゲームを含むエンターテインメント業界との親和性の高さから、現在様々な施策に取り組んでいる。
ブロックチェーンがゲームにもたらす4つのメリットとは?
――:まず、Enjinについて教えてください。
Enjinは、2009年に基盤となるEnjin Networkの提供を開始し、2000万人以上のユーザーが参加するゲームコミュニティを構築してきました。2017年にICO(新規仮想通貨公開)で1890万ドルを資金調達した後、誰でも簡単に、ブロックチェーンを用いた開発・マーケティング・取引ができる、プラットフォームの開発を進めています。
ゲーム開発者は、これからご紹介する様々なプロダクトを使うことで、トークン化されたデジタルアセットを、新規ユーザー獲得やエンゲージメント率向上などに活用できます。またこれらのプロダクトには、Ethereumベースのトークンである、Enjin Coin(ENJ)が使用されていることが特徴です。
――:それでは具体的にゲーム内にブロックチェーンを取り入れるメリットについて教えてください。
そもそも、ブロックチェーンとは分散型ネットワークを構成する複数のコンピューターに、暗号技術を組み合わせ、取引情報などのデータを同期して記録する技術です。この技術基盤を活用することで複数企業がデータベースの共同管理できるようになります。
具体的に、ゲーム・エンタメ業界にとって、ブロックチェーンの利用は大きく4つのメリットがあると考えています。まず1つ目が、デジタルアイテムの「永続性」です。従来はサービスが停止するとデータベース内の全てのデータが消えてしまいますが、ブロックチェーン上にデータを記録しておけば、データベースを複数の企業で管理できるので、そのデータを保管しておくことができます。
現段階では様々な制約もありますし、全てのアイテムをブロックチェーンにアップする(オンチェーン)必要はなく、あくまで希少価値があるものや他のサービスと連携させたいアイテムのみをアップして価値を生み出すことが適切でしょう。一部のユースケースからブロックチェーンを導入し、様子を見ながら拡大していくといった使い方をお勧めしていますね。
そして、メリットの2つ目は、ブロックチェーンを通して1つのアイテムを他サービス会社で使用可能になるといった「相互運用性」です。これには複数の企業間でのコラボレーション、運営が異なるマーケットプレイスでの売買、ゲームアイテムを担保に資金を借りる等の金融サービスとの連携といった、3種類の利用法があると考えています。
――:例えばAというゲームで「ひのきのぼう」だったものが、Bというゲームで「やくそう」として使えるというように、ゲームアイテムが複数のゲームタイトルで利用できるという世界も見えてくるわけですね。
その通りです。そして3つ目のメリットが、データの「真贋性」です。例えば画像データは誰でも簡単に複製できてしまうため、本物・偽物を見極める判断が難しいですよね。ブロックチェーン上にアップロードすることで、デジタルの画像に対して真贋を定義付けできるようになります。
そして最後が「透明性」で、ブロックチェーンユーザーはデータの履歴を誰でも確認でき、アイテムの所有履歴を一般公開することで、ゲームに関する様々なアピールが行えるようになります。
――:ありがとうございます。具体的にEnjinではどのようなサービスを展開しているのでしょうか。
Enjinはゲーム開発者を対象にしたブロックチェーンについて、5つのエコシステムを提供している会社です。1つ目が「Enjin Platform」という、ゲームとのブロックチェーン連携ツールです。このツールを用いることで開発者の方はブロックチェーン上のコードを直接触らずにアセットの発行や連携ができるようになります。ブロックチェーンゲーム開発の経験がない方でもすんなり触っていただけると思います。


また、EnjinではUnityとGodot(ゴードット)、JavaのSDKを提供しています。例えば弊社は、JavaのSDKをベースにした『マインクラフト』向けのプラグインを提供しているのですが、サーバーを所有されている方は「Enjin Platform」上でブロックチェーンのアイテムを発行・連携ができるというわけです。
提供しているサービスの2つ目が「Enjin wallet」という、暗号資産のウォレットです。いわゆるビットコインやイーサリアムのような仮想通貨を管理できることに加え、Enjinから発行されたゲームアイテムの管理もできます。
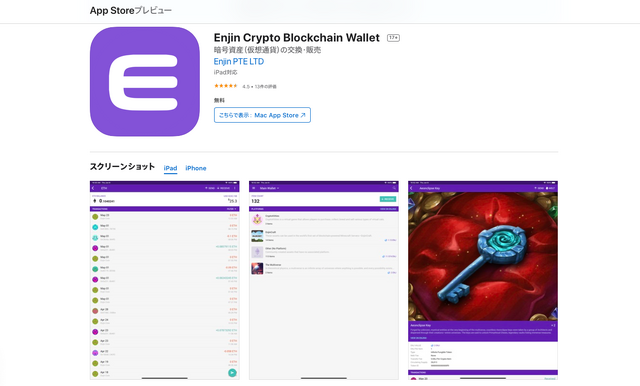
そして3つ目が「Enjin Marketplace」で、Enjinのゲームアイテムの売買を行いたいという時に、マーケットプレイスで販売したり、友人へデータの送付したりできるようなマーケットプレイスですね。
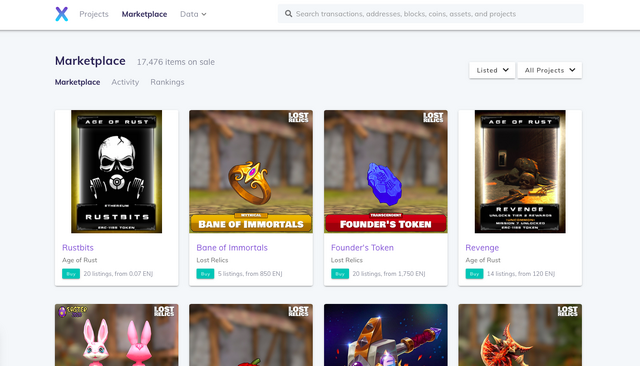
――:Enjin上でアイテム販売を行う際、クリエイターにも収益は還元されるのでしょうか?
ユーザー間で二次流通が行われた場合に、どれだけの収益を取るのかといった詳細設定が事前に可能です。ユーザーがお金儲けのためにアイテムを高額で販売するというケースを防ぐために、キャラクターの見た目を変えるスキンだけをブロックチェーンにするなど、ゲームプレイには直接影響を与えない仕様にしているゲームもあります。
そして提供しているサービスの4つ目が「Enjin Beam」という、QRコードを使ったブロックチェーンアイテムの配布サービスです。
――:Enjin Beamはリアルとバーチャルを繋げるような、有用性の高いサービスになりそうですね。
そうですね。ゲームだけに限らず、例えばクリエイターがライブストリームの時にQRコードを表示させたり、観光地でユーザーがスキャンするとNFTがもらえるといった、様々な施策が行えます。

提供しているエコシステムの5つ目が、Enjin独自のトークンである「Enjin Coin」です。2021年1月からコインチェックでの取り扱いもスタートしました。ベースとなるプロダクトを元にホワイトラベルのソリューションを提供しており、弊社では実際にマイクロソフトのAzureコミュニティのためのNFT(非代替トークン)キャンペーン等を行っております。
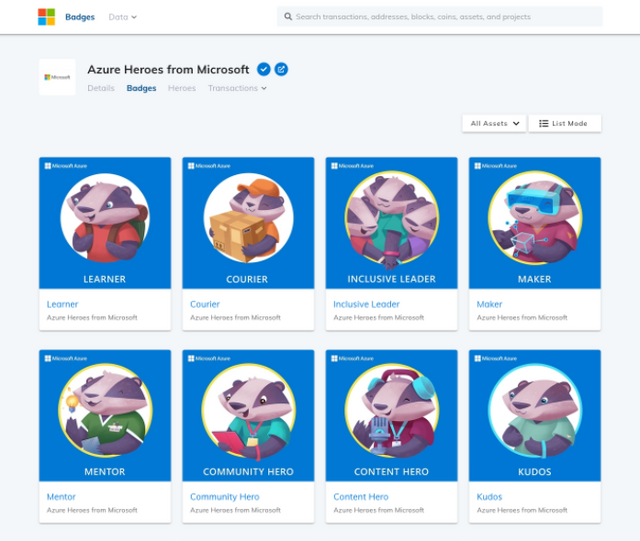
――:ユーザーの行動に、様々な価値を与えているということですね。資格情報などもブロックチェーン上では改ざんができないため、需要が高いシステムとなりそうです。
特に証明書などは海外に向けた証明が難しくなってしまうため、ブロックチェーンを利用する動きが出てきていますね。
どうなる?2021年のブロックチェーンゲーム市場
――:近年のブロックチェーンゲーム市場についてお聞かせください。
国内だとモバイルゲームの需要が多かったのですが、数年前からコアゲーマーを対象としたブロックチェーンゲームも多くなっています。例えば、『Lost Relics』というF2PのアクションアドベンチャーRPGでは、ダンジョン内で一部ブロックチェーンアイテムが入手可能です。
ユーザーはアイテムのトレードができますし、他のゲームでも使用できる設計になっています。最近日本のブロックチェーンゲームを中心に扱うメディアで記事として取り上げられたこともあり、徐々に日本のゲームユーザーが増えきている印象です。
また、最近はスクウェア・エニックスさんがブロックチェーンゲームに投資しており、バンダイナムコスタジオさんはブロックチェーンのエンジニアの採用を始めているようです。
海外ですと、ユービーアイソフトさんもブロックチェーンの研究開発に対しては積極的ですね。こういった動きがどんどん広がっていき、独自のブロックチェーンゲームの経済圏が実現すれば、面白いことになると思います。
――:最後にメッセージをお願いします。
Enjinのツールに関しては、ホームページから開発者ドキュメントをご確認いただけます。ご興味を持った方には一度Enjinを触っていただき、何かご不明な点がございましたらご質問いただければと思います。
国内だけでなく海外のゲームとの連携といったユースケースも、一緒に作っていければと考えております。もちろん企業の方だけでなく、個人の開発者の方も大歓迎ですので、ぜひお声がけいただければと思います。
ありがとうございました。
投機だけでなく、新たな価値をゲームやプレイヤーに与え、新経済圏を作り出す可能性も秘めたブロックチェーンゲーム。NFTの注目も日増しに高まるなど、今後も普及に向けた動きが加速していきそうです。