【BitSummit 14】水口哲也氏が語る「なぜ」から始まるインディーなゲーム作り
『Rez』や『スペースチャンネル5』の生みの親として知られ、近年では『Child of Eden』などを生み出したゲームクリエイター水口哲也氏。先週末に京都みやこメッセにて開催されたBitSummit 2014にて登壇した水口氏は、「Independent DNA」と題した基調講演を行い、いかに
その他
その他
『Rez』や『スペースチャンネル5』の生みの親として知られ、近年では『Child of Eden』などを生み出したゲームクリエイター水口哲也氏。先週末に京都みやこメッセにて開催されたBitSummit 2014にて登壇した水口氏は、「Independent DNA」と題した基調講演を行い、いかに
この記事の感想は?




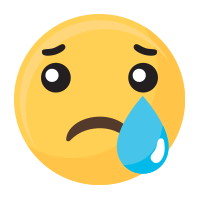

人気ニュースランキングや特集をお届け…メルマガ会員はこちら